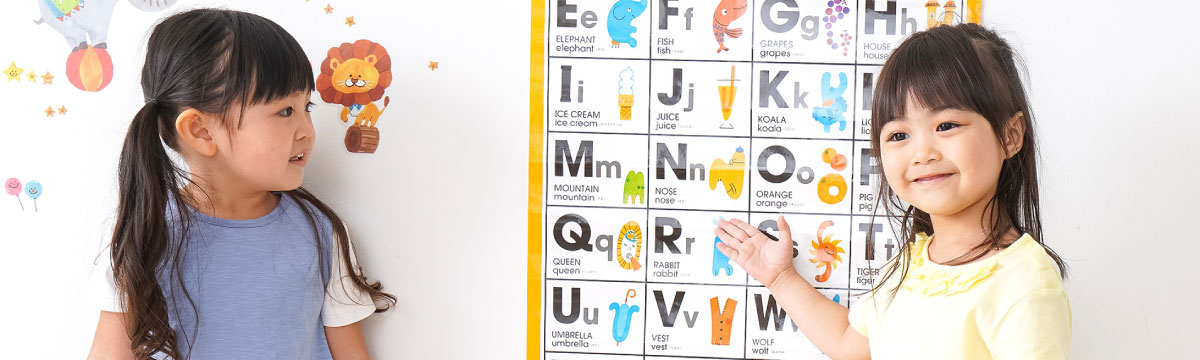育脳お役立ち情報
食育を考える2 子どもの偏食について
子どもの偏食にはいつの時代も悩まされるものです。
自宅でも、保育園でも、食事の際に子どもの好き嫌いや食わず嫌いに困ってしまった経験がある方は多いのではないでしょうか。
今回は育脳の中でも重要な食育における子どもの偏食についてご紹介します。
子どもの偏食について
栄養を考えて、一生懸命作った料理を食べてくれないというのはやはり悲しいものですし、イライラしてしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、子供に偏食があることは当たり前なのです。
なぜなら、大人と違い子どもは免疫力が低く、体もまだしっかり成長していないため、様々な外敵から自分を守る術を生まれながらに持っているからです。
口当たりの良くない食べ物や、苦みや酸味のある食べ物は本能的に「毒だ」と認識してしまい、食べることを避けるようです。
特に赤ちゃんに毛が生えた程度の1~3歳ぐらいの時期は食べ物に対しての好き嫌いが顕著です。
子どもがどうしても食べてくれないときは
小さく刻んだりすりつぶしたり、好きな食べ物に混ぜ込んだりするような方法が多く取られます。
また、見た目だけでなく味に違和感を覚える子どもにはあえて味付けを薄くして、好きな食べ物と一緒に食べることを進めてみたり、嫌いなものが食べられたときは褒めてあげるとよいでしょう。
また、子どもが好きなキャラクターがパッケージに書いてあったりするものも「〇〇もこれ好きだよ。おいしいから食べてみようよ」とキャラクターに乗ってみるのもよい方法です。
偏食は気にするべきか
幼児期の偏食はよくあることです。
極端な話をすると野菜ジュースしか食べなかった、グミしか食べなかった、というような話も耳にします。しかし過去形であることからもわかるように、偏食は一時期のものであまり深刻に気にする必要はありません。
偏食は自分の意志でやっていることですので、お腹がすいてきたら自然と食べるため、偏食による餓死や栄養失調になることは考えにくいからです。
子どもが食べないからと言って用意しないのはまた別問題です。子どもがお腹がすいたといったときに(もちろん決められた時間であることが重要です)ご飯を食べさせることができるようにきちんと毎食準備排しておきましょう。