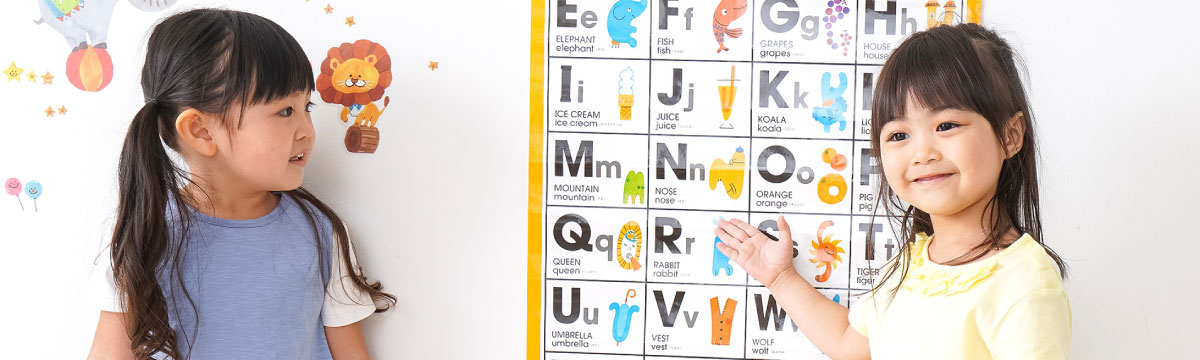育脳お役立ち情報
子どもを伸ばす子ども部屋とは? vol.2

保育園では年長さんは最長学年になります。小さな子に優しくしたりと、ふと年長さんらしい姿を見せることもあるでしょう。
あと半年で1年生。そろそろ勉強机を買わないと、と思っている家庭も多いでしょう。
今回は、子どもを伸ばす子ども部屋vol.2をお届けします。
子どもと一緒に相談しながらスペース作りをしよう!
親が一方的に机や棚を与えて家具や机を設置しても、それが子どもにとって使いやすい配置とは限らない、ということを意識しなければなりません。
大切なのは子どもと相談して決めていくことです。
一緒に相談しながら工夫することで、自分のスペースに対する愛着もわきますし、「ていねいに使おう、きれいに使おう」という気持ちも芽生えるものです。
お片付けの習慣をつけるために「生活動線」を意識すること
最近は子どもの荷物が多くて重いことが問題視されており、教科によっては学校に置いてOKとしているケースもあるようです。
子どもが学校から帰ってきて、玄関で重いランドセルを置いたら、もう別の部屋に持っていくのがつらい、ということはよくあります。
そんなことのために、玄関の片隅や階段の下に収納スペースを作るのもいいでしょう。
必要なものはそこから取り出して使い、次の日ようにまたランドセルに入れる、というパターンでも、子どもが使いやすければ問題ありません。
大切なのは生活動線がなるべく短くなるように意識すること。
何度も同じ場所を通ったりと効率の悪い動きばかりだと、いずれ片付けや収納が面倒になってしまいます。
親から見て「ここは散らかりやすいな」と感じたところに収納スペースを作るなど、臨機応変に対応しましょう。
また、ゴミ箱にふたがあって使いにくい、収納ボックスの引き出しがゆがんで全部引き出せない、すべりが悪くて力がいるなどの環境的なことが原因で片付けができなくなっていることもあります。
子どもがストレスに感じている部分はきちんと耳を傾けその要因を取り除いてあげましょう。
自分の収納スペースに合わせて持ち物を調節する
大人の世界ではすっかり認知されている断捨離。何でも取っておく、「棄てられない病」の大人は多いかもしれません。
でも子どもにとってその姿勢はあまり参考になりません。収納スペースが足りなくなったら棚を買う、引き出しを買うという発想は、最も避けたいところです。
子どもの頃から、自分の収納スペースに合わせて物を持つ習慣がつくように、必要なものと不要なものを選別する能力を養いましょう。
そうすることで、「無駄なものは買わない」という能力が自然と身に付いていきます。
リビングと玄関はきれいに保っておこう
リビングと玄関は家族がみんなで使う場所ですし、物であふれてしまいがちです。でもこの2ヶ所は普段からきれいに保つように工夫しておくと、子どもの情緒が安定するといわれています。
サッと片付くように収納に工夫をしておきましょう。