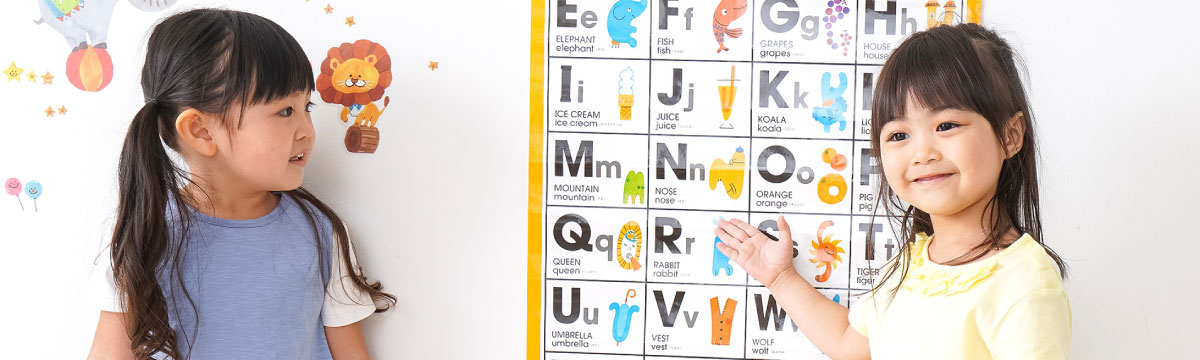幼児教育関連ニュース
特異な才能のある「ギフテッドチャイルド」国の支援は?

ある特定に分野に高い才能をもった「ギフテッドチャイルド」。この子どもたちの支援を国が検討し始めています。
文部科学省の有識者会議では、才能のある子どもを選抜して英才教育を行うのではなく、能力を持つがゆえに抱えてしまう困難を解消するための支援することが重要、という考えをまとめました。
海外では国が制度化して支援しているところが多い
数学、スポーツ、科学、芸術・・・特異な才能を持つ子どもへの才能教育は、欧米や中国、韓国などでは国が制度化して支援を行っています。
日本では1998年以降、学校教育法の改定によって高校2年で大学に入学する「飛び入学」が、千葉大学など8大学で始まりました。
これまで140人が利用しましたが、同学年との高校生活を大切に考え、受験をして大学に入る流れを大きく変えることにはなりませんでした。
義務教育中に才能がありながらも変わった行動があったりし、いじめの対象になったり不登校になったりする子がいました。
皆に同じ教育をすることが重んじられ、才能を持つ子への教育はあまり議論されてきませんでした。
才能があるのに学校になじめず困難を抱える子どもの支援へ
昨年の6月に有識者会議が立ち上げられました。才能とは何を指すか、また、対象の子どもをどう見出すかなどの検討を行いました。
委員からは「トップの人材育成だけに偏らないようにしたほうがいい」「線引きが誰かを傷つけることにならないか」など選抜には否定的な意見が多く出されたそうです。
昨年の12月に論点の整理として、ある基準で才能を定義して、その定義に当てはまる子どものみを「特異な才能」とは扱わない、と規定しました。選抜した子そもに別のプログラムを提供することは、子どもへのレッテル付けになりまねません。
そのため、「才能があっても学校になじめず困難を抱える子どもに支援をすることが中心」となりました。
現在行われている国の様々な対策
国が行う才能教育には
・大学への飛び入学
・SSH(スーパーサイエンスハイスクール事業)
・小中学生が大学教員と科学を学ぶ「ジュニアドクター育成塾」
などがあります。
SSHは2002年度から始まり、今は218校が指定されています。1校当たり5年間で5,000万円ちかい予算が配分されており、大学と共同研究を行ったり実験の設備を充実させたりしています。
一方で教育については、大学や民間事業者などで実践されています。
能力で線引きしてしまった「異才発掘プロジェクト」
2014年から始まった東京大学先端科学技術センターと日本財団が行ていた「異才発掘プロジェクト」。特異な才能のある子を支援しようと、中邑賢龍教授が実施していました。毎年小中学生300~600人の応募があり、10~30人が選抜され、それぞれの得意分野を磨いていました。
しかし、このプロジェクトは2021年に事実上終了してしまいました。大学入試の時には推薦書の作成を求められたりし、「選ばれる」ことが目的になってしまったからです。
本来の「学校になじめない子どもへの支援」からかけ離れてしまったことが要因でした。
中邑教授は「こどもを才能で線引きしてしまった」と悔やんでいるそうです。
後継プロジェクト「LEARN」
LEARNには選抜試験はなく、面接や抽選で選んだ参加者が、農家で体験活動をしたり、キャンプをしたりしています。
中邑教授は「才能は自由に学ぶ中で伸びるものであり、子どもの主体性を育むことが大切」と話しています。
まずは教師が理解を深めることが大切
有識者会議の座長である放送大学長の岩永雅也さんは、「国が英才教育を提供すべき、という議論はしていない」と語っています。
今現在、才能がありながらも学校や周りになじめずに困っている子どもを支援することが大切。その後の人生で困難を抱えたまま生きている人は少なくありません。
まずは最前線にいる教師達が、その子の才能と知識への理解を深めることが大切です。
今後は、教職課程に特異な才能を持つ子どもへの理解を深める内容を盛り込むなどを検討したい、とも語っています。
2022年1月29日(土) 朝日新聞朝刊より出典・引用しています。