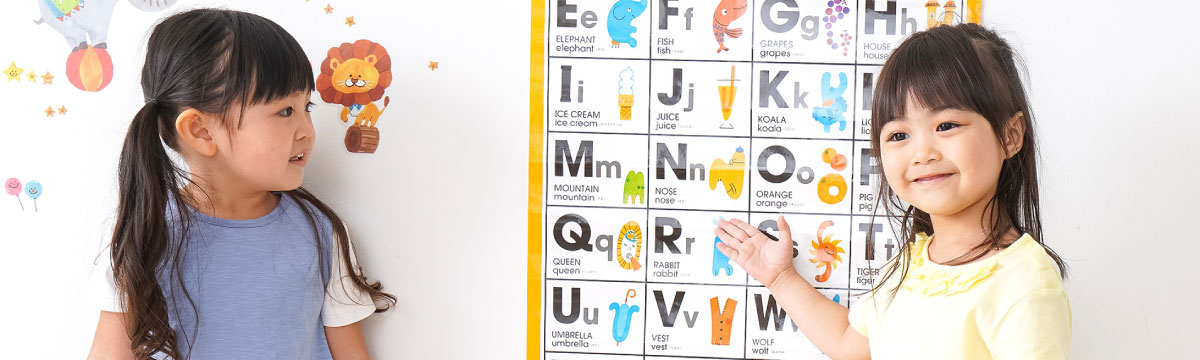育脳お役立ち情報
育脳に最適!おてて絵本のルール

前回、おてて絵本についてご案内いたしました。
今回はおてて絵本のルールをお話しいたします。
おてて絵本は育脳におすすめ!親子でおてて絵本を楽しんでみませんか?
おてて絵本のルール
どうして手を絵本の形にするの?
おてて絵本は、手を絵本の形にして話し始めます。
絵本の形にする理由は、子どもをお話の世界に誘うきっかけになること、恥ずかしさや緊張感を和らげてくれること。
もちろん、話が進んでいくと、手を絵本の形にするのを忘れてしまう子どもは多いですが、特に注意しなくてOK。
楽しくお話の世界を旅してください。
せかさない!
どんなお話にするのか決まったけれど、うまく言葉が出てこない。そんな子どもは多いです。
ポツリポツリとでも何か話すなら、合いの手をいれながら、せかさずお話を聞くようにしてください。
どうしても話さないなら、今日は気分ではないのでしょう。かわりに大人がお話してみては?
また、「主人公は誰かな?」「ひよこさん」「何をしているのかな?」「お散歩してる」「どこに向かっているのかな?」「公園」「公園で何をするのかな?」「ブランコ遊び」と言う風に、誘導しながらお話を一緒に作っていくのもおすすめです。
否定は禁止!
子どもはうんちやおならなど、汚い言葉が大好き!
つい注意したくなってしまいがちですが、ここでは我慢。注意せずに話を聞くことが大切です。
また、最初と途中で話の設定が変わり、内容のつじつまが合わなくなることが多々ありますが、いちいち指摘するのはNG。ぜひお話そのものを楽しんでください。
中には、常識外のことを言い出す子どもの姿も!(例えば、羊がニャーとないたり、ピーマンがピンク色だったり、魚が空を飛んでいたり)そんな時も常識を持ち出すのはNG。子どもの自由な想像力を一緒に楽しみましょう。
ネガティブな話の裏に隠されたものは?
殺したり死んだり。ネガティブな話をする子どももいます。
どうしてそんな話をするのだろうと、日頃から少し気にかけてあげてください。
心配しすぎなくても大丈夫。
命に興味を持っている子どもは多いです。どうして人は死ぬのだろう、人が死んだらどうなるのだろう、そんな疑問から、死ぬ話を作ることもあります。
上手に合いの手を入れよう
前回もお話しましたが、おてて絵本では合いの手が大切です。
うまく合いの手をいれることができない・・・と悩まなくて大丈夫。
子どもが「公園に行きました」と言えば「公園に行ったんだね」と返すだけでもOKです。それだけで「ちゃんと話を聞いてもらえているんだ」と子どもは安心します。
話につまったら、「大きな公園?小さな公園?」「公園で何をしたのかな」などと、簡単に答えられるような質問をしてみましょう。
親子でおてて絵本を楽しもう!
おてて絵本は、子どもがお話を作ると前回お話しましたが、厳密には子どもだけで作るのではありません。親が相槌を入れていくことで、一緒にお話を作っていくのです。
また、このページは僕、ここからはママ、その次はパパと、1つのお話を順番に話していくのも面白くておすすめ。
どんな話が出来上がるか、楽しみですよね。
お話は、メモしたり録音したりすると、後々まで楽しむことができます。