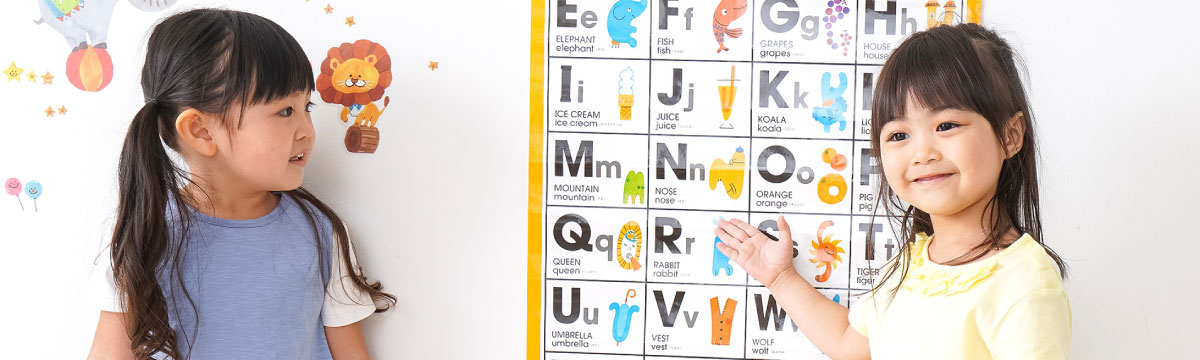育脳お役立ち情報
子どもの知的好奇心を育てるポイント

今の子どもたちの将来の競争相手はAIになってきます。
たくさんの量を一度に処理できるAIよりかしこく将来を豊かに生きる人に育てるためには、よりものごとを深く考えることができる知的好奇心をもつことが大切です。
こちらではお子さんの知的好奇心を育てるポイントについてご紹介します。
知的好奇心とは
京都大学大学院研究員の論文「知的好奇心尺度の作成」(2015年)によると好奇心には「知的好奇心」と「知覚的好奇心」の2種類があるそうです。
知的好奇心は「いろいろなことを知りたい」「なぜこうなるのか調べたい」という気持ちのこと。
知覚的好奇心は「物音が聞こえたら出どころを確かめたくなる」「気になる建物を見たら入ってみたくなる」といった気持ちです。
知的好奇心の中でも新しいことに挑戦したり、新しい物事や経験を探したりする「拡散的好奇心」と、予期しない出来事を原因がわかるまで調べたり、問題の解答を理解しないと落ち着かず納得行くまで調べたりする「特殊的好奇心」の2タイプに別れます。
どちらも学校や今後のじんせいにおいてとても重要なものです。
知的好奇心を育てるために親ができること
お子さんが人生を豊かにして生き抜くためにひつような知的好奇心。
その知的好奇心を育てるためにできることはなんなのでしょうか。
好奇心の芽を摘み取らない
「子どものなかで育つ「好奇心の芽」が花になるかは親の関わり次第」と2000年度~2010年度に獨協中学・高等学校の校長を務めた永井伸一氏が伝えています。
「これは何?「どうして?」と質問を繰り返す好奇心がピークに達した2〜3歳児を「忙しいから」「うるさい」と拒絶していませんか。
「親に話しても聞いてもらえない」と子どもが認識する5歳くらいになると「好奇心の芽」はしぼんでしまいます。
親も一緒に考える
上記の子どもの質問や疑問を否定しないことは大切ですが、大人が答えを教えて上げる必要がないというのは脳科学者の茂木健一郎氏の言。
突き放したり、答えを教えてしまうとお子さんが「自分で答えを見つける機会を永久に奪ってしまう」からです。
お子さんの知的好奇心を育てるには「どうしてだと思う?」と問いかけたり、調べ方や答えにたどり着くヒントをおしえてあげるようにすることが重要でしょう。
「どうして?」と聞かれたら「そうだね、どうしてだろうね」と一緒に考えてみたり、あえて間違ってみせてお子さんの「教えてあげたい」気持ちを引き出すのがポイントです。
親も一緒に好奇心をもつ
お子さんが「見て見て」となにかを見せてきたときに、「そんなのどうだっていい」と思うこともあるかもしれません。
しかし、そうなると「どうだっていい」といいう気持ちが冷たい反応となり、お子さんの好奇心をしぼませてしまうでしょう。
お子さんの知的好奇心を育むためには親が好奇心をもって「確かに、どうしてなんだろう」と思えるかどうかが大切になるのです。