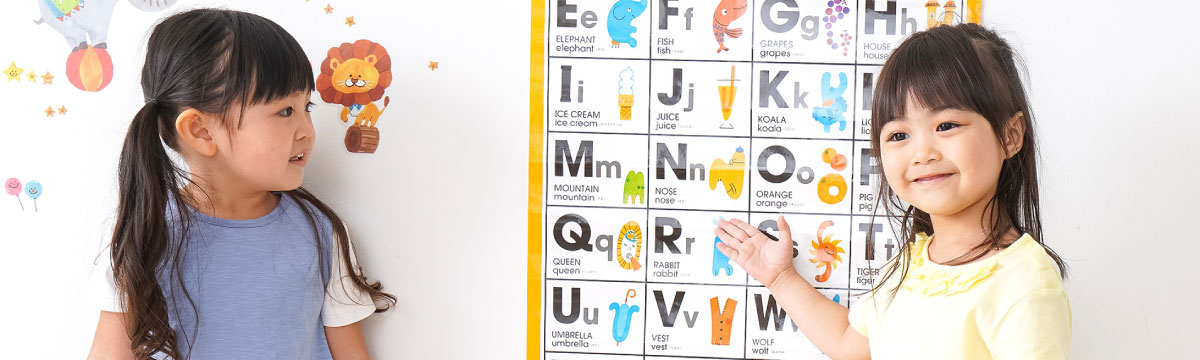幼児教育関連ニュース
「ラーケーション」で平日休暇、家族で過ごそう

子どもが保護者と一緒に体験活動などを行うことで、平日に学校を休んでも欠席とみなされない制度である「ラーケーション」。この制度は、愛知県が「休み方改革」の一環として先行導入したもので、親子のふれあいや学校外での学びの重要性を重視し、全国の自治体でも徐々に広がりを見せています。しかしながら、「家庭の経済格差が影響するのではないか」といった懸念の声も上がっています。
(※2024年6月30日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
ラーケーション制度の導入-愛知県での新しい学びと休暇の取り組み-
ラーケーションとは、「ラーニング(学び)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせた造語です。愛知県では昨年9月から、保護者との校外学習を目的として、児童生徒が自由に休む日を選べる制度が開始されました。この制度は、名古屋市立校を除く県内の公立小中高校と特別支援学校で導入されており、年間で最大3日まで取得可能です。日時や場所を含む学びの計画を記載した「届け出」を事前に学校に提出することで、その取得日は欠席扱いにはなりません。
ラーケーションで親子の新しい学びを実現、豊橋市の家族の体験とは
愛知県豊橋市にお住まいの原田友子さん(44歳)は昨年12月、当時高校2年生の長女・莉子さんと中学3年生の次女・瑚子さんと一緒に関東へ出かけました。娘たちは月曜日をラーケーションの日として活用し、日曜日を含めた2日間で東京都内の史跡などを巡りました。莉子さんが事前に行く場所を調べ、浅草の浅草寺などを訪れたほか、外国人観光客に英語で話しかける時間も設けました。
原田さんは実家の和菓子店を手伝っており、週末や祝日は仕事があるため、これまで子どもたちと一緒に宿泊を伴う遠出をすることが難しかったといいます。莉子さんの友達も多くがラーケーションを取得しており、休んだ日の授業内容も友達同士でノートを見せ合って補完しています。莉子さんは「今年度もぜひラーケーションを取得したい」と話しています。
ラーケーションの広がりとその効果、愛知県教育委員会のアンケート結果から
愛知県教育委員会は今年1月から2月にかけて、県立高校の生徒や公立小中学校の保護者を対象にアンケートを実施しました。回答を寄せた約4万9千人の保護者のうち17.3%、高校生約2万人のうち11.5%が、すでにラーケーションを「取得した」と答えています。
ラーケーションを取得した生徒や保護者からは、「家族との会話が増え、学校での学びにも自信がついた」「新しいことに挑戦するきっかけとなった」といった肯定的な意見が寄せられました。ラーケーションを導入する自治体は少しずつ増加しています。
例えば、茨城県では今年4月から、県立高校や特別支援学校などでラーケーションを開始し、市町村立の小中学校でも多くの学校が年度内に導入を予定しています。この制度は、学校外での体験や探究的な学びを推奨し、年間5日まで利用できるのが特徴です。6月には、同県教育財団がラーケーションを活用し、平日に親子で参加する遺跡発掘体験を企画し、小学生を中心に計32組、78人が参加しました。
また、山口県では少子化対策として「こどもや子育てにやさしい休み方改革」を掲げ、6月から年3日以内の「家族でやま学の日」を県立高校や一部の市立小中学校で開始しました。さらに、親子で平日に参加できる体験教室の提案や、「休み方改革月間」の11月に子連れでの県施設利用料を無料にする予定など、様々な取り組みが進められています。
ラーケーションに伴う収入格差と教員負担の懸念
ラーケーションの導入に関しては、親の収入格差が影響したり、教員の負担が増加したりする懸念があります。
愛知県内で唯一、ラーケーションの導入を見送った名古屋市教育委員会の担当者は、「休みが取れる家庭と取れない家庭が生じ、公平性に欠ける」と理由を説明しています。また、休んだ分の学習は自習で補うことになっていますが、「学校でのフォローが必要だ」という意見が出る可能性もあり、教員不足の現場ではその対応が難しいと話しています。
40代の愛知県内の小学校教員は、小学3年生の息子と1年生の娘を育てていますが、ラーケーションを取得したい気持ちはあるものの、「自分の生徒を置いて休むことには抵抗がある」と感じています。また、愛知県立高校の50代の教員は、定期考査とは別に、ラーケーションで休んだ生徒向けに追試を行う必要があり、「制度の趣旨は理解できるが、日々の業務に余裕がなく、対応に手間が増えた」と述べています。
昨年9月にラーケーションを開始した大分県別府市は、当初は平日に市外への家族旅行を対象としていましたが、「旅行に行く経済的余裕がない」という声が寄せられたため、市内や自宅を拠点とする過ごし方も認めることにしました。
また、栃木県日光市では、「保護者と一緒に『体験や学びの活動』を行う場合に取得を」と広報しており、市教育委員会の担当者は「家庭の事情が多様であるため、過ごし方を限定しないようにしている」と説明しています。
親野智可等さんの提言「体験格差への配慮とラーケーションの活用法」
教育評論家の親野智可等さんのご意見です。ネットなどを通じたバーチャルな体験が増える中で、子どもが自然と触れ合い、実際に現地に行って本物に触れることは非常に重要です。週末に休むことが難しい親がいる現状を考えると、平日を活用できるようにすることは良いアイデアだと思います。
ただし、親の収入によって体験格差が広がりすぎないよう、自治体が公営施設のクーポンを配るなどの工夫が必要です。また、教員の負担増にも注意が必要です。年に3?4日程度のラーケーションであれば、子ども自身が勉強したり、親や友達に質問したりすることで対応できると思います。