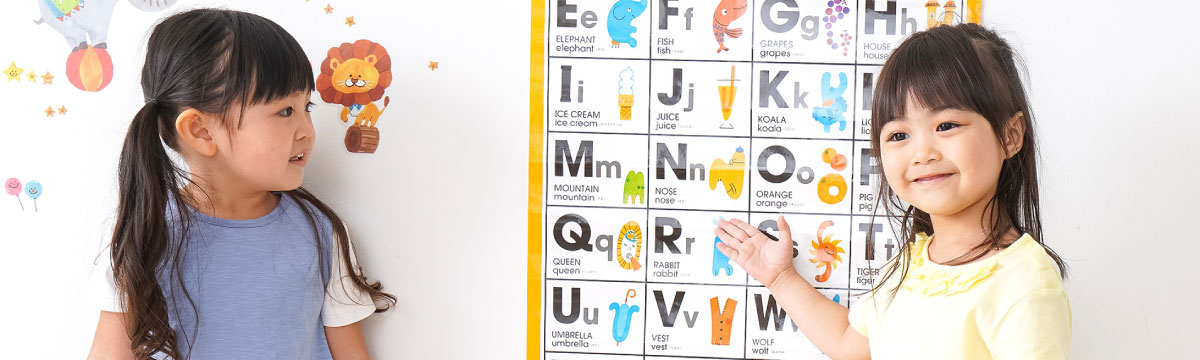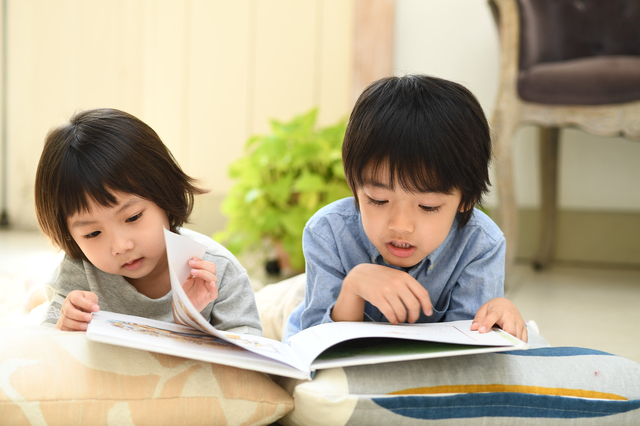幼児教育関連ニュース
子どもにどう伝える?戦争と平和

8月15日の終戦記念日、12月8日の真珠湾攻撃、長引くウクライナとロシアの戦争・・・。子どもが戦争に触れる機会は多くあります。その中で、子どもたちが衝撃的な映像や写真を目にし、心を痛めることもあるでしょう。このような状況で、大人はどのように寄り添い、戦争や平和について何をどのような形で伝えていけばよいのでしょうか。皆さまと共に考えてまいりたいと思います。
(※2024年7月28日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
恐怖心を尊重する教育のあり方について考える
「『怖い』という感情を軽視しないでください」。千葉県にお住まいの福嶋尚子さん(42歳)はそう語ります。
福嶋さんが小学校低学年の頃、学校でアニメ映画『はだしのゲン』を鑑賞しました。原爆投下のシーンでは、風船を持った少女が一瞬で焼け落ちる描写があり、その衝撃的な映像に深く傷ついたそうです。まるで自身が同じ痛みを体験したかのような感覚が心に刻まれ、それ以来、風船を見るたびにその記憶がよみがえるようになったと言います。広島を訪れた際にも、路面電車を見るたびに恐怖が蘇ったといいます。
学校や地域で再び『はだしのゲン』が上映された際、福嶋さんは「戦争の恐ろしさも、戦争がいけないことももう十分理解しました。どうかこれ以上見せないでほしい」と切実に訴えました。幸運にも無理に鑑賞させられることはありませんでしたが、友人に「もう見たくない」と話したところ、「怖がってるの?」と笑われたことが心に残ったそうです。
何を「怖い」と感じるかは人それぞれです。戦争の話題に限らず、学校や日常の中での経験が誰かにとっては辛い記憶となることもあります。もちろん、それをすべて避けることは現実的ではありませんし、他の子どもにとっては学びの場となる可能性もあります。しかし、それだからこそ、大人たちには慎重に考えてほしいと福嶋さんは訴えます。特に、学校という場は「強制力」を伴う性質を持つため、子どもたちの発達段階に合わせた丁寧な配慮と検討が求められます。
どのように伝えるべきか。残酷なシーンを見せることが本当に正しいのか。それを見直すことなく行われる教育では、かえってその意義を損なう可能性があるのではないでしょうか。子どもが「怖いからやめたい」と言ったときに叱られたり笑われたりしない学校であってほしいと、福嶋さんは願っています。
現在、千葉工業大学で准教授として教育学の研究を行う福嶋さんの言葉には、深い洞察と問題提起が込められています。
沖縄戦を深く学ぶために「戦争の構造」と体験談を結びつける教育への挑戦
戦争に関する話を聞いて恐怖を覚える理由は、必ずしもその内容が直接的に衝撃的であるからではない場合もあります。沖縄県宜野湾市で修学旅行生向けに沖縄戦のガイドやワークショップを行う狩俣日姫(かりまたにつき)さん(26歳)も、「子どもの頃の平和学習が苦手だった」と述べています。
当時の平和学習では、沖縄戦の体験者からの証言を聞くことが中心でしたが、話に登場する地名や距離感、艦砲射撃や部隊名といった用語が理解できず、記憶に残るのは悲惨な場面ばかりだったと言います。人々の死や深刻なけがといった内容は衝撃的で、「怖い」「嫌だ」という感情が強く残りました。
狩俣さんは、沖縄戦をより深く理解するためには、戦争が「なぜ」「いつ」「どのように」始まったのか、そして再び同じ過ちを繰り返さないためには何が必要かといった「戦争の構造」を学び、それを体験談と結びつけることが重要だと考えています。そのような視点を持つことで、学びの受け止め方が変わるのではないかと提案しています。
2022年、狩俣さんは沖縄戦に関連したガイドや議論を深めるための独自のワークショップを展開する会社を仲間とともに設立しました。この取り組みが評価され、同年にはフォーブスジャパンの「世界を変える30歳未満の30人」に選出されました。
「多くの子どもたちは平和学習を『大切』だと思いながらも、その内容を十分に受け取れていないことがあります。現在も戦闘が続く地域の現状に心を寄せつつ、子どもたちが自ら主体的に学びを深められる場を提供していきたい」と狩俣さんは語ります。
子どもたちの未来に「平和の種」をまく保育の取り組み
戦争や平和について子どもたちと考えるには、どのようなアプローチが適切なのでしょうか。広島県にある社会福祉法人くじら公私連携型保育所「廿日市保育園」では、その方法を模索し続けています。
この保育園では4年前、年長児を対象に広島平和記念資料館への見学を行いました。資料館の展示にはショッキングな内容も含まれていますが、広島という土地柄、子どもたちは今後、小中高の各段階で原爆について学ぶ機会が多くあります。職員たちは、「この年齢で理解できる平和とは『ケンカして仲直りすること』といった身近な体験ではないか」と話し合い、日常の保育の中で平和について考える時間を自然に取り入れてきました。
また、活動の一環として、折り鶴を折って平和記念公園に奉納したり、ピカソの『ゲルニカ』と同じ大きさの壁面に子どもや職員がアートを描くプロジェクトを実施しました。「平和ってなに?」「幸せとは何だろう?」という問いかけには、「温かい布団で眠れること」「毎日ご飯が食べられること」といった純粋な答えが子どもたちから返ってきます。
「子どもたちにとって、戦争の怖さをリアルに感じることは難しい年齢ですが、彼ら自身が毎日元気に登園している姿そのものが『平和』を表しているように思います」と語るのは、園長の広瀬英美さん(50歳)です。「いまは平和の『種まき』の段階だと感じています。いつか成長したときに、この経験が大切なことだったと気づいてくれることを願っています。そして、子どもたちには戦争の怖さを一生経験することのない人生を送ってほしい」と広瀬さんは続けます。
このような取り組みは、子どもたちの心に平和の概念を育み、その未来に小さな種を蒔く活動といえるでしょう。
「行動できる」感覚が支える子どもの心。戦争を伝える際の工夫
戦争の話題について、大人は子どもにどのように伝えるべきでしょうか。特に、トラウマ(精神的外傷)を抱える恐れがある場合、大人の対応には細やかな配慮が求められます。
日本プレイセラピー協会の代表理事で臨床心理士の本田涼子さんによれば、未就学児や小学校低学年の子どもは、現実を大人のように正確に認識することが難しいと言います。例えば、テレビで戦争や災害の映像を見た際、同じ場面の繰り返しでも、それが現在進行形で起きている出来事だと捉えてしまうことがあります。また、「悪いことが起きるのは自分のせいだ」と思い込む傾向もあり、因果関係を正確に理解するのは難しいのです。
「平和」や「戦争」といった抽象的な概念を理解できるようになるのは、一般的に小学校3?4年生頃からとされています。しかし、それ以前の年齢でも、大人の感情を敏感に察知し、怒りや不安、恐怖を強く感じ取ることがあります。
幼い子どもには、身近な話に置き換えて伝える工夫が必要です。「お友達とケンカするように、国と国もケンカをすることがあるんだ」「戦いに行くことになって悲しい気持ちになる人もいるよ」「早く平和になってほしいね」といった親の考えを交えた言葉で話すと、子どもは自分の感じ方を受け入れてもらえたと安心するそうです。
さらに、「戦争を止めるために頑張っている人たちがいる」というように、現在進行形で状況に対応している人々の存在を伝えることは、子どもがポジティブな感情を持ち、安心感やコントロール感を得る助けになります。
戦争関連の施設を訪れる際も、子どもが大人と一緒に安心できる環境で展示を見るのと、1人で見るのとでは、その印象が大きく異なります。また、募金活動をする、語り部の話を聞いて周囲に伝えるなど、子ども自身が「行動できる」という感覚を持てる経験は、ショッキングな出来事に触れた後の回復力(レジリエンス)を高めることにつながります。
このように、子どもたちが安心して学び、感じたことを行動に移せる場を作ることが、大人の重要な役割といえるでしょう。