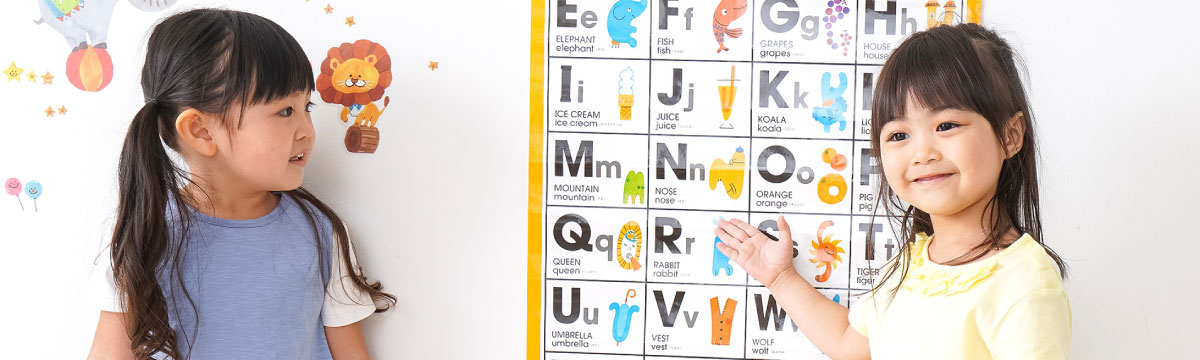育脳お役立ち情報
子どもとIT機器、うまく付き合うために大人はどうしたらいい?

今年度から全国の小中学校に一人一台端末を配布する「GIGAスクール構想」が本格的に始まっています。保育園時代からすでに親のスマホやタブレットを操作している子どもは多いでしょう。いずれ、親よりも子どもの方が詳しくなるのでは、と感じる保護者もいるかもしれません。
これからどんどん進むIT化。うまく付き合っていくにはどうしたいいでしょうか?
古い価値観は捨てる!子どもと一緒に学ぶ姿勢をを忘れずに!
今、子ども達に求められているのは、正解のない問題に対して適応して自分なりに答えを導き出せる力です。それには親の方も古い価値観は捨て去り、一緒に学ぶ姿勢が大切。もし時間が許すのなら、子どもと一緒にプログラミングを学んでみるといいでしょう。思わぬ発見があるかもしれません。
何か危険を感じたらすぐに「使用禁止」とはしないことです。
親がスマホから離れられない生活をしているのに、子どもに禁止とは言えないでしょう。
現実にどう危ない目に遭いそうになったのか、どうすれば安全に使うことができるのか、親子で一緒に対策を考えるいいきっかけと考えましょう。
親も一緒になって子どもに寄り添い、試行錯誤して考え学ぶ姿勢を見せることで、子どもは「親は味方になってくれる」と感じるでしょう。
「危ない目に遭った、親に見つかったら怒られるから隠そう・・・」子どもをこういう考え方にさせないようにするのも親の役目ではないでしょうか。
時間の区切りをつけることで、時間管理術も一緒に習得!
最近は中学校に入って初めてスマホを手にしてSNSを始める子が多いです。これを「中1デビュー」というそうですが、まだまだ使い方もに未熟です。悪口を書き込んだり、画像を拡散させたり、トラブルが最も多いのが中1です。
一律に「あれもダメ、これもダメ」とせず、親も一緒になって色んな状況を見極めて対応していく事が求められています。
ただ、ゲームやYoutube視聴などで時間がどんどん削られてしまうのはもったいないことです。
時間を区切って見るなどし、時間管理術も一緒に身に付けるきっかけにしてみるのがいいでしょう。
子どもたちも子どもたちなりに危険を認識して注意しています。様々な経験を積みながらデジタルとアナログの双方の良いところを見つけていってほしいですね。
時にはゲームも学びのチャンスに!
ゲームも悪いことばかりではありません。ゲームの上手な人に共通するのは、探究心が旺盛なことです。失敗した原因を考えてまた挑戦する能力に長けています。
ゲームや動画から何を学ぶかが大切なのかもしれません。
オンライン授業やデジタル教材が普及することで、不登校の子も一緒に学べたり、病気や障害で登校できない子が一緒に授業を受けたりできます。これは画期的なことでもあります。
学校に馴染めない子でも、興味のある分野はどんどん発展的な学習ができるようにしてあげれば、学びの楽しさが味わえるのではないでしょうか。
ゲームや動画でも、子どもの意欲や好奇心が伸びるきっかけになるかもしれません。